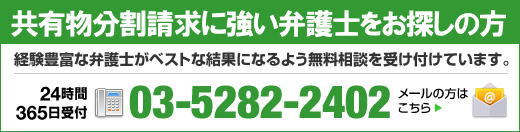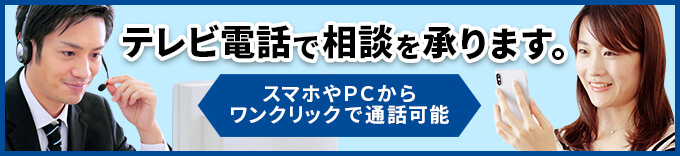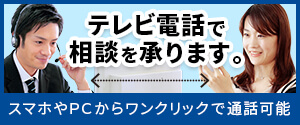共有不動産・共有名義不動産とは
それぞれの不動産について、自由に建物を建てるなどの使用、人に貸して賃料を取得する収益、売却などの処分を自由に行うことができる所有者がいます。
この不動産の中で2人以上の複数人が所有者になっている不動産を共有不動産・共有名義不動産といいます
共有不動産が生じるケースとしては、以下の場合があります。
- 遺産分割協議で不動産を共有することと定めた場合
- 遺言で特定の不動産について共有で取得させることと定めた場合
- 離婚した元夫婦の共有名義の共有不動産が残った場合
- 親子で二世帯住宅を共同購入した場合
- 名義貸しローンで共有不動産を購入した場合
この不動産を共有している場合、例えば2人で2分の1ずつ土地を共有している場合に、それぞれが土地の2分の1ずつを所有しているというのではありません。土地全体を2分の1ずつで持ち合っている関係となります。
このように不動産を共有している共有者各人が不動産全体に対する割合で所有する権利を共有持分といいます。
共有不動産・不動産の共有名義のデメリット
共有不動産、不動産の共有名義には以下のデメリットがあります。
自由に使用収益処分ができない
不動産を1人で所有していれば、不動産に居住したり、賃貸にして賃料収入を得たり、担保に入れてお金を借りたり、売却して売却代金を得たりするなど、使用収益処分を自由にすることができます。
ところが、不動産を2人以上で共有している共有不動産、不動産の共有名義の場合は、居住、賃貸、担保借入、売却は自分1人の意思で行うことができず、他の共有者の了解を得る必要があります。
このように共有不動産、不動産の共同名義は、1人で所有している不動産とは違って自由に使用収益処分ができないことから。これが共有不動産、不動産の共有名義の大きなデメリットとなります。
相続で共有者が増えると相続人探しが難しくなる
そして、共有不動産、不動産の共同名義を放置すると、登記記録の共有者が既に死亡しているということも結構あります。そうするとこの登記記録の持分権利者の法定相続人を戸籍謄本を取り寄せるなどして探す必要が出てきます。
登記名義人に子供がいる場合は比較的容易なのですが、子供がいない場合は兄弟姉妹が法定相続人となる事が多くなります。そうすると死亡した名義人が死亡から出生までの戸籍の取り寄せだけでは足りず、名義人の両親の死亡から出生までの戸籍の取り寄せまでも筆必要となります。
そしてこの兄弟姉妹が名義人よりも前に死亡していたとしてもこの兄弟姉妹の子供には代襲相続権があることからこれも調べる必要があります。
よって、共有名義人に相続が発生し特に子供がなく兄弟姉妹が法定相続人になっている場合相続人探しが難しくなります。これが共有不動産、不動産の共同名義のデメリットとなります。
相続で多数の法定相続人が現れると使用収益処分が難しくなる
相続で共有者が増えると相続人探しが難しくなるというデメリットを説明させていただきましたが、これによって非常に多数の法定相続人が現れるケースも珍しくありません。
私の経験でも20年くらい前に死亡した人の法定相続人が20人を超えたこともあります。
ただでさえ、不動産の使用収益処分の同意を取り付けるのが難しいのに相続によって多数の法定相続人が現れると同意をとり付けること自体がほぼ不可能となります。結果的には競売で処分するしかなくなることも多くなります。
このように、相続で多数の法定相続人が現れると、不動産の使用収益処分が難しくなるというのも共有不動産、不動産の共同名義のデメリットとなります。
共有者間で不公平感を生じやすい
不動産を2人以上で共有している場合、共有者はそれぞれ持分割合に応じた権利を持っています。
ただし不動産は金銭と違って物理的に分けることができないので、共有者のうちの誰かが居住し、他の共有者が居住していないということもよくあります。
そうすると居住している共有者は持分を持つことで不動産に居住するというメリットがありますが、居住していない共有者にとっては持分を持っていても何の意味もないことになります。
このように共有者の間でも居住している人と居住していない人がいる場合には、共有者間には不公平感が生じやすくなります。
この共有者間に不公平感を生じやすいというのも共有不動産、不動産の共同名義のデメリットとなります。
共有不動産・不動産の共同名義は解消できる
これまで述べたように、共有不動産、不動産の共同名義には多くのデメリットがあります。
この共有不動産、不動産共同名義のデメリットを解消するために設けられたのが共有物分割請求権です。
共有物分割請求権は、共有不動産、不動産の共同名義の解消を希望する人に対して強制的に解消を実現することができる権利です。共有物分割請求権についての詳しい解説はこちらをご覧ください。
具体的には以下のとおりとなります
売却を求める場合
共有不動産の売却を求める場合、競売を命じる判決を得ることを目指します。
これは共有物分割請求における最終的な手段ですが、物理的に分ける現物分割ができない事例が非常に多く、全面的価格賠償も代償金を用意するのが難しいことから、結果的に競売を命じる判決が下されることが少なくありません。
他の共有者が不動産を失いたくないと考えれば時価で不動産の買取をせざるを得なくなります。また競売を嫌がることによって共同売却ができることもあります。どちらもできない場合は競売によって売却せざるを得なくなります。
ただ実際にはこの原稿を書いた2023年の時点においても不動産購入希望者が多いことから競売でも時価ないしそれ以上の金額で売却されている事例も多くあります。その結果、売却を希望する人が共有物分割請求によって、他の共有者が時価で買い取るか共同売却か競売による売却で売却することができ、共有不動産、不動産の共同名義を解消できます
買取を求める場合
共有物分割請求の中に全面的価格賠償があります。これによって他の共有者の持分を強制的に買い取ることが可能となります。
そのためには、買取希望者が持分を買い取るのが相当であること、代償金支払能力があることを証明する必要がありますが、これができれば強制的に買い取ることができます。
これは訴訟によって実現することができるのですが、交渉段階においても、相手方が訴訟提起をされること、鑑定費用を一部又は全額負担させられることを嫌がれば、持分を買い取ることができることもあります。
いずれにしても全面的価格賠償を用いることで相手方の持分を買い取ることができ、これによって共有不動産、不動産の共同名義を解消することが可能となります。
全面的価格賠償についての詳しい解説はこちらをご覧ください。

著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設
共有不動産の関連ページ
- 共有不動産トップページ
- 遺産分割協議によって共有不動産を取得しましたが、この共有状態を解消できませんか?
- 遺言によって特定された共有不動産を取得しましたが、この共有状態を解消できませんか?
- 親子で共有の二世帯住宅を建てたのですが、この共有状態を解消できませんか?
- 離婚した元夫や元妻との共有不動産がありますが、この共有状態を解消できませんか?
- 名義貸しローンで共有不動産を取得しましたが、この共有状態と名義貸しローンを解消できませんか?
- 遺留分減殺請求で共有不動産を取得しましたが、この共有状態を解消できませんか?
- 土地の共有名義の解消方法
- 共有不動産・共同名義不動産の時価売却
- 共有不動産で他の共有者の持分を買い取りたいのですが、買取に応じてもらえません。何かよい方法はありませんか?
- 共有不動産から発生する賃料収入を共有者の1人に独占されています。賃料の分配を受ける方法はありませんか?
- 私が居住していない共有不動産に居住している人に対して賃料請求できませんか?
- 共有不動産に居住している共有者から持分割合に応じた固定資産税の負担を求められました。応じなければいけませんか?
- 共有不動産で他の共有者の持分が競売にかけられました。どうすればよいですか?
- 共有不動産の持分を共有持分買取業者に売却することを考えています。弁護士に共有物分割請求を依頼した場合との違いは何ですか?
- 共有不動産で他の共有者の持分を買い取った不動産業者から交渉を持ちかけられました。どうすればよいですか?
- 当方は不動産会社です。共有不動産の共有持分を買い取ったのですが他の共有者との交渉がうまくいかなくて困っています。
- 共有不動産の共有持分権利者に対して債権を有しています。債権回収をするのによい方法はありませんか?

著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設